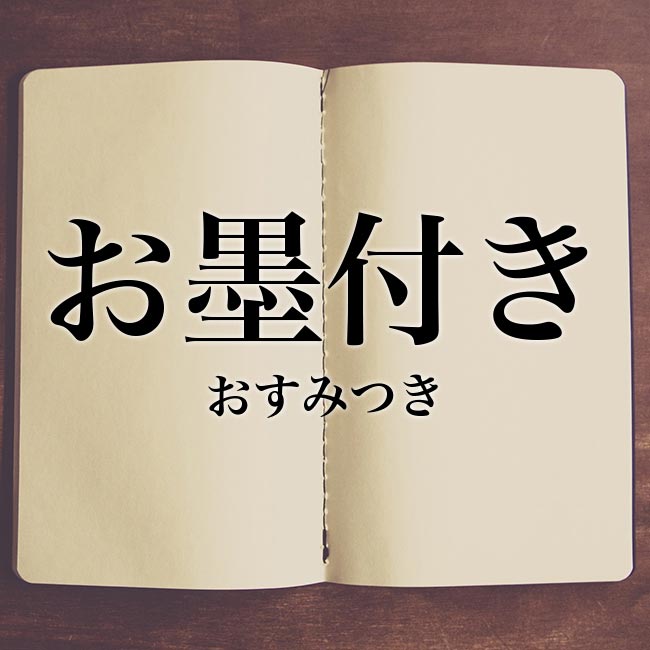
「お墨付きをもらう」とはどういう意味ですか?
お墨付きの語源・由来
その文書が「お墨付き」と呼ばれた由来は、署名や署名を図案化した「花押」が、墨で記されていたことによる。 ここから、権力や権威のある人が与える保証を「お墨付きを与える」、その保証を貰うことを「お墨付きをもらう(得る)」と言うようになった。
キャッシュ
折り紙つきとお墨付きの違いは何ですか?
「お墨付き」は地位や権威のある人が認めることです。 「折り紙付き」は地位や権威は関係なく、他人が品質を認めることです。
「太鼓判を押す」とはどういう意味ですか?
たいこばん【太鼓判】 を 捺(お)す
(証明のために大きな判をおす意から) 絶対まちがいのないことを保証する。
「お墨付き」の読み方は?
御墨付き(おすみつき)の意味・使い方をわかりやすく解説 – goo国語辞書
キャッシュ
「お墨付き」の例文は?
【例文】有名ソムリエのお墨付きのワインを買う。この論文は世界に通用すると教授のお墨付きをもらった。先生のお墨付きのお店を紹介してもらった。皮膚科医のお墨付きの洗剤を使っている。
「お墨付きをもらう」の言い換えは?
お墨付きを得る
| 意義素 | 類語・類義語・言い換え・同義語 |
|---|---|
| ある事実を確実なものとする証拠を得ること | 確証を得る 確証が出る 確証が得られる 裏付けが取れる 担保される 保証される 確保される 確証される 鑑定される 特定される お墨付きを得る 太鼓判が押される 太鼓判を押される ウラが取れる 確認が取れる 突き止める |
「折り紙付き」の言い換えは?
そのものの価値や実力などに定評があること折り紙つき折り紙付き保証つき保証付き太鼓判つき太鼓判付き極め付け極めつけ
間違いないと保証することわざは?
「折紙付(おりがみつき)」とは「そのすばらしさに間違(まちがい)いがない」という意味(いみ)の慣用句(かんようく)です。 「その人やものが持(も)っている価値(かち)は、本当(ほんとう)にすばらしいものだ」と保証(ほしょう)する場合(ばあい)に使(つか)われます。
「墨付き」とはどういう意味ですか?
すみ-つき 【墨付き】
写本で、実際に文字の書かれている紙。 その枚数を記すときにいう。 武家時代、将軍や大名などが臣下に後日の証拠として与えた、黒印を押した文書。 また、その黒印。
「お墨付きをもらう」の別の言い方は?
お墨付きを与えるお墨付きを与える太鼓判を押す判を押す保証する請け負う信用を与える請け判を押す
「お墨付き」の別の表現は?
お墨付き
| 意義素 | 類語・類義語・言い換え・同義語 |
|---|---|
| 公式の許可または承認 | 裁可 裁許 認可 認定 公認 御墨付き 免許 オーソライズ |
| 述べられている事実が真実であることを証明する文書 | 信任状 免状 免許証 認可証 証明書 免許鑑札 認可状 免許状 証状 保証書 証書 確認書 鑑札 証票 認定証 御墨付き 免許 |
「お墨付き」の対義語は?
「お墨付き」と「折り紙つき」の対義語
「お墨付き」には特に決まった対義語はありません。 「折り紙つき」の対義語は「札付き」です。
なぜ折り紙付き?
対して「折り紙付き」とは、絶対に間違いないと信頼するに足る保証付きという意味です。 書画や骨董(こっとう)に付ける鑑定書として、奉書(ほうしょ)などを折って用いたことから転じた言葉です。 権威や力を持つ人が「これで良い」と認めるときに用いるのが「お墨付き」。
勘違いされやすいことわざは?
「明日デートだから、浮き足立ってるよ」は完全に間違っているわけです。「気が置けない」 〇「気を使わないでいい」 ✖「油断できない」「役不足」 〇「実力に対して役や仕事が軽い」「檄を飛ばす」 〇「自分の意見を広める」「割愛する」 〇「惜しいと思うものを手放す」「煮詰まる」 〇「議論が十分になされ、結論寸前の様子」
「茶腹も一時」とはどういう意味ですか?
一杯のお茶を飲むだけでも、しばらくは空腹をしのげるものです。 少しばかりの物でも、一時しのぎの助けになるということを表現した言葉です。
「墨付く」の古語は?
すみ-つ・く 【住み着く】
居つく。 [訳] ましてこの場所にはだれもかれも居ついていらっしゃるので。 夫が妻のもとへ続けて通うようになる。 夫婦関係が定まる。
ありがとうの反対言葉は何ですか?
ありがとうの反対語は「あたりまえ」
実は、ありがとうの反対語は『あたりまえ』。
「ごちゃごちゃ」の言い換えは?
ごちゃごちゃ
| 意義素 | 類語・類義語・言い換え・同義語 |
|---|---|
| 汚くて無秩序な | 汚い 乱雑 ごっちゃ しどろ もじゃもじゃ 擾々たる ごった ごしゃごしゃ むさ苦しい 雑然たる 擾擾たる もしゃもしゃ ごじゃごじゃ むさくるしい |
| ほとんど努力せずに | ごちゃごちゃ |
折り紙付き なぜ折り紙?
折り紙付きの語源・由来
折り紙付きの「折り紙」とは、紙を横半分に折った文書のこと。 平安末期より、公式文書や贈呈品の目録として用いられていた。 そこから、江戸時代には、美術品や刀剣などの鑑定書を「折り紙」と呼ぶようになり、確かな品質が保証されている物を「折り紙付き」と言うようになった。
多くの人が勘違いしている言葉は?
トップ5をご紹介します。「失笑する」「敷居が高い」「(話の)さわり」「なしくずし」「悪びれる」第1位『 ハッカー 』77.4%第2位『 確信犯 』73.0%第3位『 他力本願 』68.8%第4位『 破天荒 』68.3%第5位『 姑息 』62.6%
